DIYであれば費用は5千円ほど。開口は糸鋸で開けるのが良い
屋根換気口をつける
福島県田村市にある平屋、2021年に「みんなの0円物件」さまを通じて取得しました。
この物件、賃貸用にするにはあまりにも奥まったところにありますので、民泊として利用できないかいろいろ模索しているところです。
民泊利用には様々な行政手続きを経なければいけないため、その間に物件を快適に利用できるようリフォームしています。
今回は、囲炉裏の煙を排気するための換気口を天井に取り付けます。

囲炉裏のある家なんて今どき珍しく、民泊の売りにもしたいと考えています。
が、建築当初に囲炉裏用の排煙設備を取り付けるのを忘れていたそうで、前の所有者も囲炉裏は使っていなかったそう。
このまま囲炉裏を使うと、薪をくべるたびに煙がすごいことになり部屋に煙が充満します。

そこでまず考えたのは、換気口を囲炉裏の真上に取り付けることです。
幸いにもこの物件は平屋で、しかも囲炉裏のあるダイニングキッチンに屋根裏は無さそうです。
構造的に3層(野地板+防水シート+屋根(金属、たぶんガルバリウム鋼板))という、比較的穴あけのやりやすいものでした。
取り付けた換気口は①室内側のもの、②屋根側のものの2種類です。
・スライド式で開閉ができる
・250㎜×300㎜角
・雨が入り込まないようにRを描いている
・排気口の格子の目が粗いので、防虫のため網戸の網を出入り口に張り付ける
どちらもモノタロウで購入しました。
安すぎませんか、モノタロウ。。。


開ける手順
まずは室内側の換気口を作ります。
脚立で手が届く高さだったので助かりました。
角型レジスターの換気部分のサイズに合わせてケガキをします。
本体をビス止めする必要があるため、ビス穴よりも内側、小さく開口するように注意します。

ケガキした線に合わせて穴をあけていきます。
この「下側から板を切っていく作業」が一番大変でした。
私は丸ノコ、インパクトドライバー、鑿、ハンマー、バールなど、いろいろ駆使しましたが、1時間くらいかかりました。。。

インパクトドライバーにつけたドリルビットで、ケガキした線上に穴をたくさんあけ、そこを丸ノコで削ったり、鑿とハンマーで貫通させたり、バールで抉ったりと、あの手この手ですこしずつあけていきました。
おそらく一番楽なのは、インパクトドライバーでケガキした線上に小さい穴をあけ、そこから糸鋸で屋根材もろとも切っていく方法です。
この時点では、屋根材がどれだけ固いかといったことがわからず、室内側の木と屋根材を別々に処理しようとしてかえって苦労しました。

室内側を開けましたので、続いて屋根側を開けていきます。
屋根に上って作業しますので、安全確保しながら登っていきます。
家の前後に丁度良いヒノキが2本あったので、ロープをくくって屋根の上にぴんと張るようにします。
脚立で屋根のふちまで登り、そこからはぴんと張ったロープをつかみながら屋根の上に上ります。
屋根の勾配はそこまで急ではないので、普通に立つことができました。

屋根側でも、換気口のビス穴より内側部分で開口するようにケガキをします。
ケガキをした線上にインパクトドライバーの金属用のビットで穴を開けます。
最初はグラインダーでないと切断できないかなと思っていましたが、薄い鋼板だったのでハサミでえっちらおっちらと切っていくことができました。

機能としては、煙が抜ける穴が開いていて、雨と虫が入らなければそれでOK。
ルーフィング材も穴に合わせて切り取り、無事に貫通です。

無事に両側が開口したら、角型レジスターとウェザーカバーをビス止めしていきます。
悲しいことに、室内側の開口穴と屋根側の開口穴がずれていたせいか、角型レジスターの開閉がうまくいきません。
開閉板の立ち上がる部分に屋根材が干渉してしまいます。
仕方がないので、レジスターを表裏反転して取り付けます。
こうすれば、開閉板は室内側に立ち上がりますのできちんと機能します。
また、開閉するためにいちいち本体のつまみをいじる必要のないよう、つまみにひもを通して、ひもを引っ張ることで開閉できるようにしておきます。
これで室内側はOK。
続いて屋根に上って、ウェザーカバーをビス止めしていきます。
この時、防虫対策用に網を取り付けます。
普通の換気扇用のウェザーカバーであれば、そのまま取り付ければ問題ないと思いますが、林の中の一軒家ということで、防虫対策がいります。
網戸の網を利用してウェザーカバーのビス止め面と格子が開いている面の2か所に網を張ります。
ビスと一緒に揉みこむことで固定してしまいます。
屋根の加工ということで、防水対策として、ウェザーカバーのビス穴、周囲にコーキングを施します。
さらに、横殴りの雨による室内への水の侵入を防ぐために、ポリカ波板を設置します。
本来、ウェザーカバーは壁面に設置し、開口部が下を向くようにすることで雨が入らないようにするものです。
今回はそれを屋根に取り付けているので、開口部が真下を向いていないため、横殴りの雨に対して侵入を許してしまう可能性があります。
そこで、開口部の前にポリカ波板を設置して横殴りの雨に備えます。
煙は逃がしつつ、外からの雨を防いで、水がたまらないよう屋根からは浮かせます。

色々つけ方は考えられますが、手持ちの資材と手間を考えた結果、T字型の金物を角度つけてウェザーカバーに留め、端材の木でポリカ波板を受けるという形にしました。
見た目は不格好ですが、屋根上で目に付く場所ではなく、問題があった場合に後で試行錯誤しやすいよう、このまま様子を見たい思います。
作業完了後、囲炉裏を使いましたが、きちんと排煙されているようです。
火の勢いが強く、もくもく煙が上がるようなときには上昇気流のおかげできちんと煙が抜けていきます。
一方で、火の勢いが弱く、ゆらゆら煙が上がるようなときは、室内に煙が拡散してしまいます。
こういう煙も排煙するには、焼き肉屋のテーブル上にあるような機械的な排気に頼るか、茅葺のように天井面全体から排煙する必要があるでしょう。
雨風を防ぎつつ、囲炉裏も最大限活用できるように、昔の家はよくできていたんだなあと改めて感心します。
何はともあれ、煙の軽減という当初の目標は達成できました。
所要時間は3時間ほど、かかった費用は換気口部材2,190円+899円=3,089円です。余った資材を活用したので、これだけで済みました。
コーキング材や網の費用も加味すると5千円ほどでできそうです。
これからは囲炉裏ライフを楽しみつつ改良していきます!
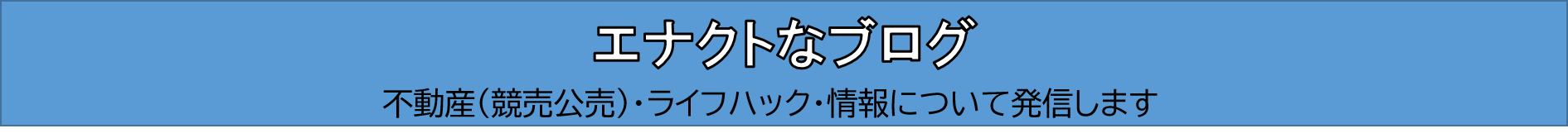


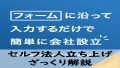
コメント