過去物件振り返りシリーズ
今回はアパート、いわゆる”共同住宅”を狙った時のお話。
まずは物件スペック
築 32年
広さ 1091㎡・161㎡(土地・建物:軽量鉄骨造)
現況 6室中4室が入居
基準価格 358万円(924万円で落札)
周辺 駅近
備考 借地権
今回の物件に目を付けたポイントとしては以下です。
・収益性の高い共同住宅
・入居者がすでにいる
・駅近
・収益性の高い共同住宅
一般的にアパートやマンション一棟物は同じボリュームの戸建てよりも収益性が高いです。
ワンルーム4万円の相場でも、2部屋ある物件で8万円かといわれるとそうではないですよね。
これは、居住するという行為についてベースとなる最低限の価格があり、これは部屋のボリュームにあまり左右されないため、もう一つはある一定上のスペースはオプションとみなされるようになるためだと思います。
まず、ある場所に住むとなると、現代日本では当然のようにお金を払う必要があるという認識があります。
つまり、ワンルームだろうが4LDKだろうが、ある場所に居所があるということに対して対価(居住対価と仮にします)が発生するのです。
おそらくこの居住対価はワンルームの相場よりやや低い程度(2万円ほど?)で、これは大きなボリュームの戸建てでも変わらないのではないかと思います。
物件の賃貸相場を居住対価+活動スペースと考えると、ワンルームは居住対価にほんのわずかな活動スペース、ということで2万円+0~2万円程度、広い間取りは2万円+3~5万円程度となるのではないでしょうか。
そして、活動スペースは必要分より狭いととても不愉快に感じる一方で、活動スペース分以上の余剰スペースはそこまで快適性を生み出すものではないと考えられます。言い換えると、スペースのニーズが広さに伴って低下するといえます。(広すぎるとお地価なかったり持て余したりしますよね)。
以上のことを考えると、ワンルームの1平米当たりの単価(居住対価+余剰スペース)が広い間取りにそのまま適用されず、相場が頭打ちになるのは、ある一定以上の間取りは余剰スペースになりえ、余剰スペースに払う対価は居住対価や活動スペースに対する対価よりも低いためと考えられます。
と長々自己流の考えを書いてきましたが、要は
”狭い部屋の多世帯の集合住宅は、同じボリュームで1世帯のみが住む戸建てよりも収益性が高い”
という、それだけのことです。
・入居者がすでにいる
今回の物件はすでに入居者がいる状態で、これから買い付ける身として考えるとこれは非常にありがたいです。
何より、家賃収入が所有権移転後にすぐに入るためです。
さらに、家賃相場がすでに分かっていることになりますので、価格設定のミスも防げます。
逆に言うと、価格の上限がある程度見えてしまっているともいえますので、リフォームして高く貸すことをもくろむ大家さんは嫌がるかもしれません。
ただ私の場合はリフォームに費用をかけないようにしているので、今回の場合はこれはプラスに働かう要素です。
年間収益の見通しが立てやすく、利回りが現実的になることも大きいですね。
・駅近
何はともあれ益地加奈物件はやはり魅力的です。
”不動産”はその名の通り、立地を動かすことはできません(間取りや外装は後からでも調整できる)。
否かであろうとも駅の知覚はヒトの活気、賃貸需要に直結するでしょうから、駅地下であるだけで物件の価値は上がります(競争も激化しますが…)
以上のポイントから入札をしたのですが、この物件のもう一つの特徴は
・借地権が設定されている
ことです。
借地権とは、土地を借りてそのうえで物件を使用している、ということです。
つまり、建物の所有者とは別に土地の所有者がおり、建物所有者はこの土地の所有者に賃料を払っている状態なのです。
ここで問題になるのが、競売物件で建物を取得したものの、新しい所有者に対してもこれまで通り土地を貸してくれる保証はない、ということです。
また、土地を貸すのはいいとしても、前の所有者の方が土地の賃料を滞納していた場合(ローン返済ができずに競売になっているため十分あり得ます)、たいていはその滞納分を新所有者が支払う必要があります。
そのため、借地権が設定されているような物件の場合、必ず関係者に事前に話を通しておき、買受け後に問題なく使用できるかを確認する必要があります。
今回の場合、地主さんは地元のお寺さんで、電話したところ新しい所有者と契約のまき直しをする用意があるとのことでした。
借地権で地代を毎月払う必要があるために見込み収益は下がりますが、それを考慮しても魅力的な物件だったため、息巻いて入札しました。
結果、競り負けましたがね。
まだまだ共同住宅を取得するまでの道のりは遠いです。
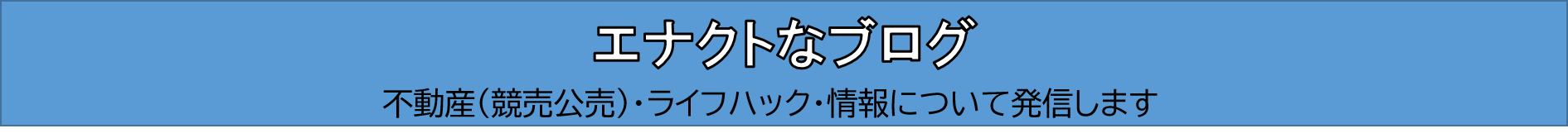



コメント