結論:生業を見つけて、認識の幅を広げて、実現力を高めよう
FIREの流行
最近、FIRE(Financially Independent Retire Early; 経済的自立と早期退職)という言葉がやたらと流行っています。(自分でそういう話題を探しているせいもありますが)
FIREはつまり、生きていくのに困らないだけの資産(預金、株式など)と資産所得の見込み(配当所得、不動産収入など)を作っておいて、お金のために辛い思いをする仕事を辞めて自分らしく生きよう、という考え方です。
皆さんはFIREしたいですか?
そう問われたときに、おそらく多くの方が「今の仕事生活の負担とそれがなくなった時の自分」というものを思い浮かべて、時間と給与の変化のバランスを考えると思います。
「負担がすごく軽くなるし、贅沢もしないから仕事辞めようかな」
「時間が増えればもっと自由になるけど、貯金が少ないから仕事はまだ辞められないかな」
などなど、「給与」v.s.「自由」という構図で考えるでしょう。
これは現代の仕事が「嫌な仕事に時間を割く代わりにお金がもらえるもの」という認識が前提にあるからです。
生きるためには何をするにもお金が必要→お金を得るには時間を犠牲にして仕事をする必要がある→自由な時間が無くなる…
多くの人がこのループに入っており、じゃあ抜け出すにはどうすればいいか、そう考えたときにFIREという考え方と実践している人が取り上げられて大流行したわけですね。
上記のある意味絶望的なループから抜け出せそうな希望として自由な生活の魅力を謳うFIREが現れたわけです。
でも、FIREを考える前に「自由とは何か?」、「どういう生き方」が合っているのかを煮詰めていかないと、FIRE後に思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。
自由とは認識と実現のギャップの少なさ
皆さんにとって「自由」とはどういう状態でしょうか?
私にとって自由とは次の状態です。
「自分の認識と実現能力の一致」
かみ砕いていうと「やりたいと思ったことをやれる状態」です。
当たり前に思えることですが、こうやって具体的な言葉で自由を表現すると、具体的に自由に近づくステップが見えてきます。
自由がない状態というのは例えば
・時間があったらできるはずのことが仕事のせいでできない
・お金があったら買えるはずのものが生活のことを考えると買うことができない
などの状態です。
「自分の認識と実現能力の一致」に対応させると、
「~なはず」という部分が「認識」の部分
「~できない」の部分が「実現能力」の部分です。
多くの場合、実現能力にフォーカスが当てられ、
「○○はできそう」、「××はできなさそう」→「だからFIREを目指そう/FIREを目指さない」
と考えます。
しかし、もう一つの大切な部分である「認識」について深く考えている人が少ない気がします。
上の例を認識を変えて捉えてみると、
「できるはずのことは時間が必要か?他のやり方はあるか?細かくできるか?」
「買えるはずのものは本当に必要なものか?他の手段で手に入らないか?」
というように、目的と手段を問い直すということです。
自分の実現能力の範囲内に収まるように認識を変えることができればそもそも不自由さは感じません。
なぜならやりたいと思ったことをやれているからです。
さらに言うと、現在の認識の範囲外のことはできるとも思っておらず、自分が自由かどうかを省みる時にも判断に影響を与えません。
例えば、江戸時代の人はメールを送れないことに不自由を感じませんが、現代の我々は通信の不具合などでメールが送れないと途端に不自由を感じます。
なぜなら、江戸時代の人は情報を伝える手段としてメールがあることを認識していませんが、現代人はメールの存在も自分がメールができることも認識している(にもかかわらずできない)からです。
こう考えると自由は相対的なものであり、人それぞれで環境や経験により変わるということになります。
要は、知らないことは選べない、選べないことに対しては自分ができるかできないかもわからないし、自分が自由かどうかも何とも言えない、ということです。
しかし、現在の自分の状態からFIREをするかどうか、生涯どういう生き方をするのかを決めてしまうのは、自分の認識が今後一切変わらない、という前提を置いてしまっています。
認識が変わらず、実現能力だけが変化する生き方は非常に息苦しいものだと想像できます。
他人の語る理想的で素晴らしい選択肢があったとしても、実現できないときに自分の能力を責めるほかないからです。
自由を感じるのはFIREしていようがいまいが「自分の認識と実現能力の一致」が重要であり、認識も実現能力も変えられるということを覚えておく必要があります。
日本人的仕事観「生業」
私はあまり仕事という言葉が好きではなく、なんとなく生業の方がしっくりきます。
仕事は「休んだり」「変えたり」「引退したり」できるというの捉え方は、西洋的な考え方のような気がします。
プライベートと仕事はきっちり分かれており、人生の中の奉仕の時間が仕事であり、仕事をしているときは自分の人生とはまた違う時間を生きている、と捉えられているのかもしれません。
一方で生業は生きるために行っている行為というニュアンスが感じられ、人生とほぼイコールと捉えられるものと思えます。
つまり、「生業を引退する=人生を終わらせる」ようなものです。
こう考えると、生活の糧を得ている行為(いわゆる仕事)を辞めるFIREなんて考え方は生業とはなじまないといえます。
そして、日本人に良くなじむのは仕事よりも生業の考え方でしょう。
仕事のオンーオフがうまく切り替えられないのも、長期休暇を許さない文化も、バケーションを楽しめない習慣も、引退後に時間を持て余してしまうのも、日本人が仕事になじまないから。
どちらかというと、生活=生業として、いつも生業のことを考えたり、上手く生活の中の時間でバランスを取ったり、生業を生涯続ける、という生き方の方が自然に感じられます。
生業が見つかればそもそもFIREをしたいという願望も生まれない気がします。
生業は生活と労働のバランスが取れているわけですから、生業を辞めようというのは生活を辞めようというのに等しいです。
FIREが日本人に合っているのかどうかはわかりませんが、時間があり余った時にその時間をうまく活用してゆったりと充実させられるというのは少数派なのかもしれません。
多くの場合、時間を持て余して結局また仕事らしきことをしてしまうというのが多いと聞きます。
FIREを目指すというよりは生業を見つけ、生業を生活の中に溶け込ませることを意識するのが良いのです。
そして、生業が見つかったらあとは自分が納得のいく生き方になるような内容にし、生活とのバランスを意識することです。
他人との比較ではなく、自分の生業の中で納得できるものを身につければそれで良い。
生業の中で実現力を高めれば自由で充実した生活という、本来FIREをする意味が自然と備わるのだと思います。
まだ思い付きの域を出ていませんが、FIREという新鮮なコンセプトが先走っている感があったので、書き出して整理してみました。
したらな!
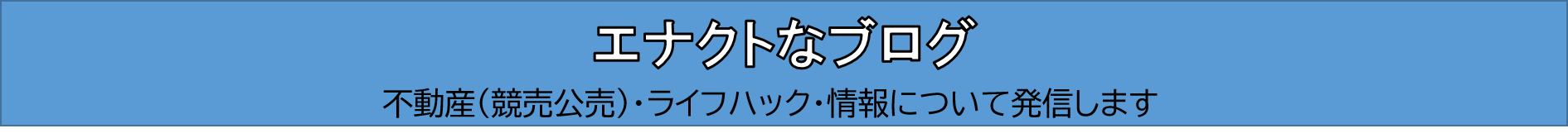


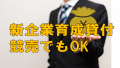
コメント