少し遡って…
令和2年9月頃に入札した区分(マンション・アパートの一部屋)の物件について、
お話ししたいと思います。
この物件は私が競売での物件取得を目指し始めた初期の物件で、
かつ初めての区分物件だったので色々と調べていたのを思い出します。
物件スペックは
築 H3年
広さ 65㎡(部屋)
現況 貸借人あり(6.5万円/月)
基準価格 185万円
周辺 駅近・都市部
備考:近々大規模修繕工事あり・管理費滞納あり(当時65万円)
入札しようとした決め手は
・すでに借りて住んでいる人がいる=取得時点で家賃収入発生
・同様の理由で、表面利回り&実質利回りが計算できた(私は約20%で計算)
・執行官(裁判所の調査員みたいな人)とのやり取りがまとも(交渉・契約が問題なさそう)
・駅の近くで、将来の売却益も悪くなさそう
といった、貸すにも売るにもパフォーマンスが高い物件だったからです。
不動産取得に当たっては、将来の不確実性(空室リスク・補修工事・家賃減損等々)を織り込んで、期待する利回りを厳しめに設定するものです。
例)今ポータルサイトで出ている物件周りの賃料設定から相場が8万円だとすると、計算は築古を考慮して7万円、修繕費用も目に見えない瑕疵(かし:物件の正常利用を妨げる要素)があるかもしれないから修繕費として30万円くらい上乗せして・・・
こうして物件取得に諸々かかる費用と見込みの収益を計算したうえで、利回りから入札価格を決めるので、結構抑えめの入札になることが多いです。
現在は(というかずっとらしいですが)競売物件の落札価格が高騰しているみたいで、私みたいな弱小個人ではほとんど落札できません。
10件くらい入札して1件しか落札できていません。
それも、市街化調整区域(都市計画法で、むやみに建物を建てたり建て替えたりが難しい場所)の物件ですので、競売物件を狙う業者さんは歯牙にもかけないようなものだったのでしょう。
市街化調整区域の場所にある建物は、再建築の可否が行政の判断に委ねられるため、売却時に
「購入する人は再建築ができないような場所の築古を買うだろうか?いや、買わない!」
という事情から、値下げや指値受け入れをしなければいけないと考えるために敬遠されるのです。
ただ、私が取得した物件は行政からの再建築も認められるであろうという見込みですので、
おそらくは大丈夫でしょう(楽観)。
話がそれましたが、この区分の物件も競売市場の高騰の煽りを受けてか
350万円ほどで落札されており、売却基準価格185万円の約2倍ほどの落札金額でした。
管理費滞納(約65~90万円)を全額負担するとなると、取得だけで400万円以上となっています。
おそらくはすぐに売却するのでしょうが、賃貸に出した時の利回りが高く見積もっても
(6.5*12*0.95(不動産管理業者手数料)-管理費ー固定資産税-火災保険)/400=利回り約15%
ですので、ちょっと狙いに行くには怖かったです。
とまあ、こんな感じで物件取得時はネガティブに、かなり安パイを狙ってますので、まだまだ次の物件取得までにはかかりそうです。
また今度過去の競売物件の見直しを綴りたいと思います。
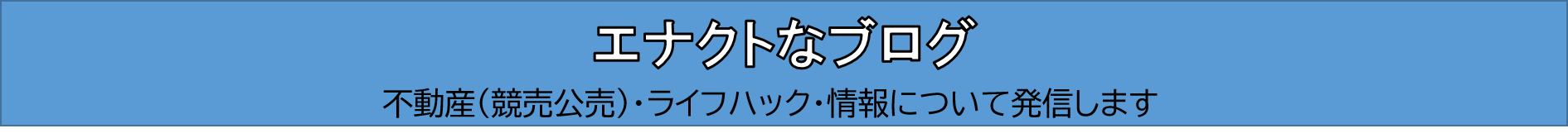

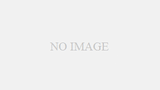

コメント