貨幣は互恵的利他の外在化のために生まれた…っぽい
税金発祥説
壮大なテーマですが、お金のことを考える切り口として興味深いテーマということで最近本を読んでいて気になりました。
種本はこちら。
貨幣の起源について税金発生説ではこう捉えます。
「国が各個人から雑多で取り扱いづらいリアルな物品を調達するして集積していたのでは非効率。労働や物資やサービスについて同質で抽象的な共通基準となる代替物が必要だ。だから貨幣という基準を作ってこれを集めればいい」
こんな流れで貨幣が生まれ、交換が生まれ、資本主義が生まれたと考えます。
つまり、国や資本主義が別々に成立したと考えるのではなく、国や税金システムというルールがまず成立し、それから貨幣が生まれて資本主義が成立するという流れです。
一般的な貨幣→交換制度→税金→国という流れとは逆で非常に興味深いです。
ただ、個人的にはこの説はしっくりきません。
というのも、リアルな物品が取り扱いづらいとはいえ国の権力をもってして、ある所からは米、ある所からは羊、ある所からは絹…というような租税制度でもきちんと成立していた時代はあったでしょうし、これが不便だからといって貨幣という抽象物に切り替えてそれを流通させるってものすごく大変なのではないかと思うからです。
ですので、国が貨幣を作って市民へ浸透、という方向より、市民間での交換文化から国が制度化、という流れの方があり得そうです。
負債発生説
上の本でもう一つ紹介されていたのが、貨幣の負債発生説です。
「コミュニティでは貸し借りが起こる。コミュニティの規模が大きくなると個人間の記憶を頼りに貸し借りを成立させるのは難しくなり、貸し借りの記録(帳簿)が必要になる。何をいくら借りているのかという負債が抽象化され、数となり、数をやり取りする道具として貨幣が生まれた」
つまり、人と人との貸し借りが大規模なコミュニティ内でも成立するようポータブルに、保存と交換可能な形態になったのが貨幣ということです。
数字という概念の概念が生まれたのも負債を表現するため、という考えも述べられています。
物々交換の規模を拡大すると時空間的な広がりが生まれ、大きいものは運ぶのも大変、運んでいるうちに腐るものだと価値も減る、時間的な保存もこれまた難しい、だから腐らない金属貨幣を基準にしよう、というよく耳にする説明とも適合するのではないでしょうか。
民法でいうところの相殺(互いに同質な債権債務を打ち消す)も可能になってコミュニティ内のやり取りが円滑になるというメリットもあったでしょう。
AさんがBさんに羊を5頭貸して、BさんがAさんにヤギを5頭貸していた時を想像しましょう。
AもBも羊とヤギが必要だから借りているのであって、借りた目的を達成するまでにはある程度時間が必要でしょう。
時間の経過とともに羊もヤギも年を取って借りたころの元気さ(価値)はなくなるかもしれません。
かといって元気なうちに返してくれ、という時限付きの貸し借りは不便です。
そこで、動物の代わりに動物と同じ価値の持つ別のもので代替しようという発想が生まれます。
2者間のやり取りであれば代替品はまた別の物品で済んだかもしれません。
しかし、CさんとAさんの間でも貸し借り、DさんとBさんの間でも貸し借り、といったように貸し借りの場に人が増えるとどんどん複雑になり、記録しておかないと間違いも起きます。
物品の価値判断も人それぞれだし、物品のリアルなやり取りも移動と保管を伴うので大変です。
「じゃあ、記録(帳簿)にあるAに貸したやつ、それをチャラにするからAから借りてるやつ返さなくてもいい?(相殺)
後、Bに貸してるやつ、Cが貸してることにして、俺はCからなんかもらうわ。BはCに返しといて(債権譲渡)」
みたいに帳簿上で打ち消しあったり負債を付け替えたり、みたいなことも起こったかもしれません。
さらに、帳簿上でいちいち記録するのも大変なので、やり取りしている当事者間で完結できるように手段(貨幣)とそのルール(貨幣制度)が生まれたのかもしれません。
これにより帳簿が時空間的に拡大しました。
裏切りと信用
ルールは貨幣という手段が有効であるために欠かせません。
というのも、コミュニティの中に裏切るやつがいるからです。
裏切るやつは自分だけが得をしようとして、帳簿の記録を無視して借りたものを返さなかったり、貸した価値以上のものを取り立てたりするやつです。
こういう裏切り者がコミュニティにいると正直者が馬鹿を見る目に合い、結果的に貨幣は意味を成さなくなります。
そうならないためにも、裏切り者には罰が必要です。
どういう裏切りをしたらどういう罰があるのか。
これを決めたものがルールです。
ルールがあれば相手は裏切らないだろう、この信用が貨幣に意味(価値)を持たせ貨幣を中心とした取引を持続的に成立させます。
また、裏切り者には罰を与える一方で、被害者には損失の補填をしなければいけません。
この時、全く同じ物品を与えるというのは難しいというような場合でも、貨幣であれば補填がしやすいです。
つまり、物品のみでの経済では「裏切られる=補填し難い損失」ですが、貨幣経済であれば「裏切られる=補填できる損失」になるという効用があります。
互恵的利他の外在化
裏切り者の排除のためのルールという考え方は心理メカニズムの成立の上でも重要な要素です。
あるコミュニティで進化が漸進的に進むには以下の条件が必要といわれています。
①コミュニティが閉鎖的。つまり流出しない。
②コミュニティが持続的。つまり、過去の情報が未来へ引き継がれる。
③コミュニティ内で互いが識別可能。つまり、個体と行動を紐づけられる。
村社会をイメージするとわかりやすいですが、このような3条件が満たされたコミュニティでは、だれがどんな人物であるか、どういった行動を取ったのかが互いに認識できるため、裏切り者は排除されます。
閉鎖したコミュニティなので裏切ってもとんずら出来ず(コミュニティ外で一人では生きていけません)、裏切ったという事実はコミュニティ内で広まり語り継がれ、誰が裏切ったのかがわかってしまいます。
こうした環境下では誰が裏切り者であるかと同じように、「誰が信頼に足る取引相手か」ということも重要になります。
信頼できる人であるかどうかは「互恵的利他」行動をするかどうかで測られます。
互恵的利他とは単なる利他行動、他者のための行動に見返りを期待するものです。
この見返りは即座に貰えなくても、後々返ってくるものであれば問題ありません。
先の裏切り者が淘汰されたのと同じように、互恵的利他行動を取る個体であることはコミュニティ内に広まり、互恵的利他行動を取る個体の周りには互恵的利他行動を取る個体が増えます。
互恵的利他行動は他者を助ける行動ですが、そうすると上で述べた「貸し借り」の関係が生まれます。
貸し借りの複雑化が起こると貨幣が生じるのは上で述べたとおりです。
上では物のやり取りで話をしましたが、物のやり取りを抽象化すると互恵的利他をやり取りしていることになります。
危機を救ったり、手伝ったりという無形の物のやり取りの一部に物品の交換があるというイメージです。
互恵的利他の外在化とは、つまり、個体の能力や頼りがいがある、過去に互恵的利他行動を取ったことがある、といった個体に内在化している価値を外に置いて保管や運搬や広く交換ができるようにしたものが貨幣、ということです。
あいつにモノをあげた、窮地を救った、などといった互恵的利他、貸し借りの関係を数量化し、持ち運びできるように個体と切り離したものが貨幣の起源ではないかと考えています。
ルールが価値を担保する
貨幣の価値を担保するのがルールであり、ルールを破ると罰が下るシステムの信頼性が貨幣の価値、つまり交換可能性に基づく人の行動を促します。
もし貨幣を差し出してサービスやモノが受け取れないし、差し出さない相手に罰もなく裏切りが得するような先が見えるのであれば人は貨幣に価値を感じられないでしょう。
貨幣を機能させるためにルールがあり、ルールが貨幣に価値を与えたといえます。
ギブをする人に富が集まる訳
互恵的利他をよくする個体は多くの相手に貸しを作っている個体です。
多くの貸しを作っているという噂はコミュニティ内で広まります。
自分に利益をもたらしてくれそうな人の周りには人が集まり、富が生まれ得ます。
上で述べた貨幣の起源からすると。貨幣と互恵的利他は交換可能であり、互恵的利他を確保できなくても貨幣があれば互恵的利他を得られます。
しかし、そもそもが互恵的利他を獲得するのが目的なのであれば、互恵的利他を発揮して交換できるのであれば始めからそれをすれば良く、また貨幣を経由するより直接互恵的利他を与えた方が魅力的といえます。
これがGiveをする人が富を得る、つまりは互恵的利他をたくさん獲得できる理由なのではないかと感がられます。
ここでのポイントは互恵的な利他であることが重要で、贖いきれない、相手のキャパシティを超えたようなギブは貨幣の様な交換性を損ないます。
交換できないのであれば返す必要もなく、返す必要のない相手にこちらから互恵的利他を与える必要はないし、互恵的利他を与えなくても損(噂)はないわけです。
一方的なGiveは互恵的利他の観点からすると成立しない考えということですね。
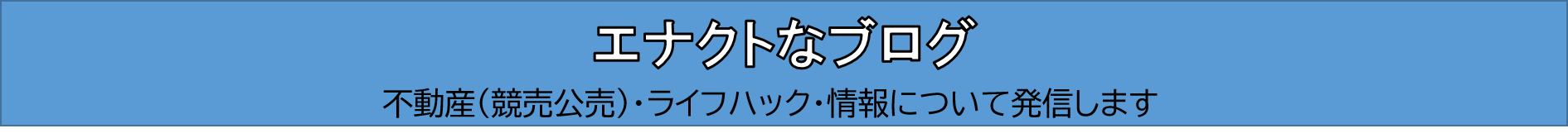
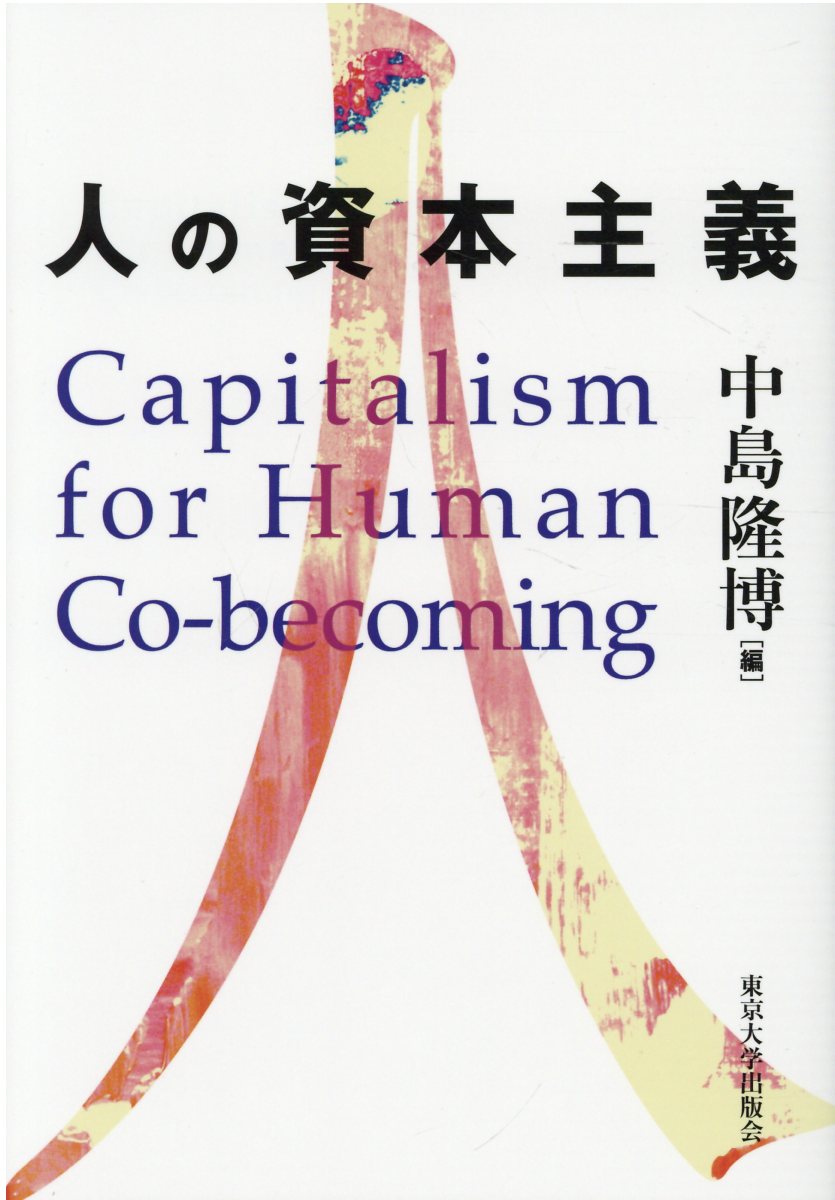


コメント